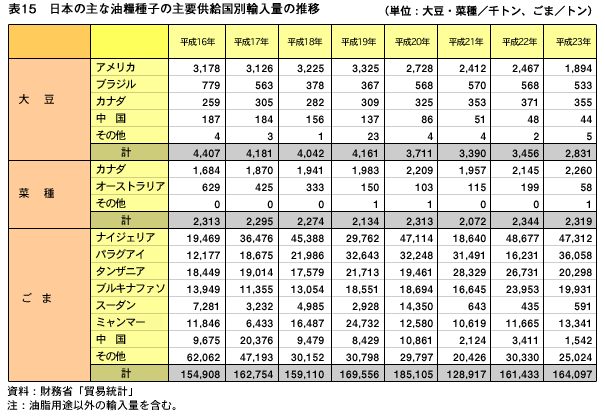一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。

平成23年に日本で利用された油脂原料は509万トンとなっています(表14参照)。ちなみに、平成17年は約600万トンでしたから、この間に90万トン減少したこととなります。これは、同じ期間に大豆搾油量が308万トンから、23年には206万トンにまで減少したことによるもので、一方、菜種の搾油量は約10万トン増加しました。
油脂原料のほとんどは海外からの輸入原料で、米ぬかが商業的にはほぼ唯一の国産原料となっています。昭和30年代までは菜種が有力な国産原料でしたが、いまでは搾油に仕向けられる量は全国で700トンしかありません。伝統的な日本食を彩るごまも、国内生産は統計数値には上らない数量となりました。十分な農地面積がない、収量が低い、栽培が難しい、気候が適していないなど様々な理由により国産原料は衰退してきました。その中で唯一の国産原料といえる米ぬかは、精米所で発生したものを集荷していますが、変敗が早く進み保管ができないため、新鮮なうちに集荷し、すぐに抽出を始めなければなりません。また、スターチ製造の副産物であるとうもろこし胚芽も同様の問題を抱えています。
これに対し、輸入に依存している油糧種子は保管が可能で、計画的な搾油が可能になるというメリットがあります。このため、製油工場のほとんどは原料が搬入される港湾地帯に立地しています。
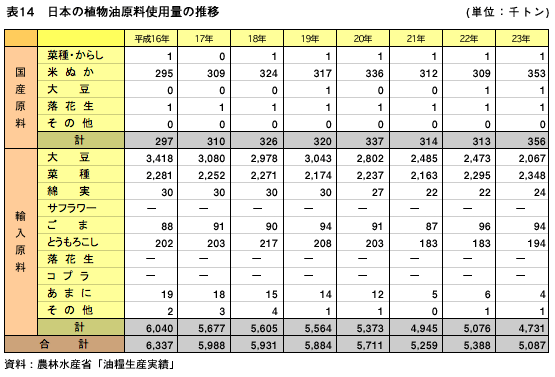
油糧種子はどのような国から輸入しているのでしょうか。大豆と菜種は、世界の油糧種子需給で述べましたとおり供給できる国が限られています。大豆についてはアメリカとブラジル、菜種についてはカナダとオーストラリアが有力な原料供給国となっています(表15参照)。この中でも主力のアメリカとカナダについては、それぞれの生産者団体との定期的な交流を持ち、原料の安定供給の確保に努めています。
大豆や菜種とは異なり、ごまは30カ国近い国に供給を依存しています。ごまは収量が低く、機械化農業に適していない作物であるため、先進国では栽培が行われず、開発途上国に供給を依存しなければならないのが実態で、また、それぞれの国の供給力が小さいことから、多くの国に依存しなければならないのです。