|

―満州の大豆産業の発展-
19世紀後半から、満州(中国の東北部。現在の遼寧、吉林、黒竜江の3省と内モンゴル自治区東部あたりを総称するのが一般的解釈のようです。清王朝を起こした満州族などが居住していた地域とされています。)が世界最大の大豆生産地域として登場し、大豆生産の拡大に伴って大豆搾油業が発展することとなります。大豆は満州内で搾油されるとともに、大豆と大豆粕は主に日本、中国に輸出され、やがてヨーロッパへも輸出されるようになりました。
満州における大豆産業の発展が、日本の大豆搾油業の黎明に結びつくこととなります。
(1)1800年代後半の大豆搾油業
History of Soybean Crushingは、「世界の近代的な大豆搾油業は満州で誕生した」と述べています。
大豆生産の発展は、まず人口の増加により支えられました。1890年における満州の人口は500万人程度でしたが、漢民族などの同地域への移動が促進され、1900年には1,000万人、1913年には2,000万人にまで増加しました。この大量の人口流入が大豆生産に拍車をかけ、1900年以降の大豆搾油ブームを引き起こしました。
1926年の南満州鉄道会社の記録によれば、1860年代以前には、満州では麻の実の搾油が行われていたが、その後それら搾油工場が大豆の搾油を始めたとしています。工場の規模は小さく、人力あるいはロバが圧搾機を動かしていました。主要生産物は大豆油で、副産物の大豆ケーキは使役用の家畜や牛の飼料として活用されていました。既に中国の他地域への輸出が行われており、1864年に443トンの大豆油、50,900トンの大豆ケーキ、49,300トンの大豆がNewchwang(現在の営口市、以下、営口と記す)の港から輸出され、1867年には、それぞれ1,390トンの大豆油、70,300トンの大豆ケーキ、60,300トンの大豆へと拡大しました。1896年に、満州に最初の蒸気機関を動力とする鉄製の搾油装置(香港製)が導入されましたが、その他は先に述べたような人力や畜力に依存する小規模な工場で、100kgの大豆から抽出される大豆油は9kg程度でした。
| * |
ここでは、搾油工場と記していますが、近代的工場ではなく家内工業の延長であったと理解するべきで、中国では「油房」と称されていました。 |
1894年から1900年に先述の在営口英国総領事として駐在したHosieは、この時期における満州の大豆産業の発展について正確に記録をした人物でした。氏の記録によれば、このころ大豆とその加工品(大豆油及び大豆粕)は満州の最大の輸出産品にまで成長しており、1899年には、大豆254,348トン、大豆粕236,543トン、大豆油8,627トンが輸出され、250万英国ポンドを獲得したと推計されています。
このころ満州の大豆生産は555,000トンを上回り、その多くが中国南部(広東、厦門など)に供給され、そこで大豆搾油が行われ、大豆粕がサトウキビ農場の肥料として利用され、更にジャワ島のサトウキビの肥料として広東から輸出されていました。しかし日清戦争が満州の大豆産業を変える大きな転機となり、同戦争終了後は日本が満州の大豆、大豆粕の主要輸出先国となって、中国南部地域向けの輸出を上回ることとなりました。日本へ輸出された大豆粕は、稲作の肥料として利用されました。当時日本ではニシン(鰊)粕が農業に利用される主な肥料でしたが、価格高騰によりニシン粕に代る肥料として大豆粕が利用されました。ニシン粕は油分が多いため、作物に害を与える昆虫が群がるという欠点がありましたが、大豆粕は油分が少なく、窒素、リン酸、カリの成分が豊富であるという利点がありました。現在のように家畜の飼料として利用されることは少なかったのは、当時の日本の食生活で畜肉を食べることが少ないことに加え、家畜に与えるより、すぐれた肥料特性を耕種作物に利用することがより合理的とされたためと考えられています。また、四足を食べないという仏教の禁忌が影響していたとも考えられます。
(2)1900年代初頭 大連の搾油業の繁栄
1900年代に、満州の大豆産業に大きい変化を及ぼす2つの事柄が生じます。一つは日露戦争で、これに勝利した日本は、満州地域における鉱山、鉄道の開発を始めとする権益をロシアから割譲されることとなります。日本では満蒙開拓団が結成され、満州の豊かな農業資源を活用する途が拓かれました。もう一つは南満州鉄道の完成で、満州の大豆とその加工品の貿易に大きい変化が生じました。
営口には多くの大豆搾油工場が稼働し、満州最大の大豆産品の輸出港として栄え、1909年には34,430トンの大豆油、324,000トンの大豆粕、215,400トンの大豆を輸出していました。これに次ぐ輸出港は鴨緑江河口のAntung(現在の大韓民国安東市)で、鴨緑江流域の生産地からの河川輸送による大豆集積地であることから搾油工場が展開され、満州第2の輸出港となっていました。
しかし1905年の南満州鉄道の完成により、同鉄道の南端に位置する大連が重要性を増し、大豆搾油工場が進出することとなり、1909年には営口に並ぶ大豆産品の輸出港へと発展し、やがて抜き去ることとなります。
1907年には、日本の大豆搾油業にとって初めての海外進出が行われました。
1890年代後半から、満州産大豆と大豆粕の日本向け輸出は日本の大手商社が取り扱っていましたが、大連における大豆搾油業の進展に呼応して、1907年に日清豆粕製造株式会社(現在の日清オイリオグループ株式会社の前身)が設立され、営口に出張所を設置するとともに、大連に当時としては最新の蒸気機関駆動の搾油工場(日清豆粕製造所)が建設されました。その名称から、主産物が大豆粕の製造にあったことが分かります。
「日清製油(株)60年史」(1969年11月30日刊行)を紐解くと、「当時、満州農産資源の中心であった大豆およびその製品の豆粕については……豆粕はすぐれた肥料価値をもち…」と記され、「日清戦争後、豆粕が満州から本格的に輸入されて以来、豆粕は魚粕に代ってしだいに肥料界の王座を占めつつあった。」と続けられています。
しかしこの時期においては、安価な労働力に依存する小規模な旧式の搾油の方が、多額の資本を投下する近代工場より収益性が高かったようで、クサビ式の搾油装置はその後も長く使用されました。蒸気機関を利用する近代工場は、上記の日清豆粕製造所のほかには、中国系のAnglo Chinese Trading社が当時のハルピンにあるだけでした。
【 図5 日清豆粕製造所大連工場(1908年ごろ) 】
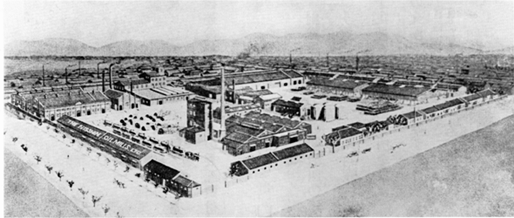
(3)満州の大豆生産量は500万トンがピーク?
満州地域には多くの製油工場(油房)が林立し、大豆とその加工品は満州地域からの重要な輸出産品となり同地域の経済を支えましたが、大豆生産の豊凶の変動、日本における肥料市場の変動に加え、満州産大豆と大豆油が欧米にも輸出されることに伴う国際相場の変動という要因が登場し、大連における大豆搾油が順風満帆で進んだわけではありませんでした。しかし第一次世界大戦(1914~1918年)の勃発が、満州の大豆搾油業の苦境を救う要因となりました。戦争の勃発により、自国内の搾油工場の操業が困難となった欧米諸国、とくにアメリカが満州産大豆油の大量輸入を始め、満州における大豆搾油に一種のブームをもたらしました。
ところで、満州ではどれぐらいの数量の大豆が生産されたのでしょうか。南満州鉄道(株)が刊行した「満州における大豆」は、1926年(満州の大豆生産のピーク)の状況について次のような記録を残しています。
| 満州の大豆生産量 |
387万トン |
| うち、搾油用に利用された割合 |
48.6% |
| 輸出された大豆油と大豆粕 |
41.1%相当量(大豆換算) |
| 地域内で消費された大豆油と大豆粕 |
7.5%相当量(大豆換算) |
| 搾油工場数(小規模の油房を含む) |
447 |
| 1日当たり大豆油生産量 |
1,587トン |
| 1日当たり大豆粕生産量 |
528,000トン |
| 大豆粕の主要輸出先 |
日本(生産量の76%) |
満州地域の大豆生産量は、最大時には500万トンに達し、その半分が搾油に用いられたという推計もがありますが、大豆情報センターは搾油に利用された大豆は最大で200万トンではないかと推計しています。しかしこの時期には満州が世界最大の大豆生産地域であったことは疑いもなく、満州産大豆の供給が世界の大豆搾油業を押し上げる推進力となりました。
(4)日本の大豆搾油業
満州から大量の大豆輸入が可能となったことは、日本の製油業にも活気をもたらすものとなりました。1900年前後の時期には、神戸は大連に次ぐ搾油基地を形成していました。搾油されていた油糧種子は菜種、綿実が主なものでしたが、満州からの大豆の供給が確保できることとなったことから、蒸気機関を推進力とする大豆搾油工場の建設も進められました。1919年には神戸地区には25の搾油工場が操業し、1,520万ポンド(約68万トン)の植物油が製造されていました。
大豆搾油の目的は、大豆粕を製造し肥料需要に応えることで、大豆油のほとんどは欧米、特にアメリカに輸出されていました。アメリカの大豆油需要は、日本からの輸出と満州で操業する日本企業からの輸出で支えられていたのです。その背景には、先に述べた第一次世界大戦の影響がありましたが、1912年に日本からアメリカに輸出された大豆油は6,033トンで、その後1919年に至るまで、毎年3万トンを超える大豆油がアメリカに輸出されました。今では想像もできないことですが、満州という大豆供給源の存在が、それを支えた要因でした。
満州からの大豆供給の増加は、日本の大豆生産量にも影響を与えました。日本の国産大豆の生産量は最大で50万トンに達したとされていますが、満州からの輸入の増加に伴い急速に減少しました。この事実だけを見ると、輸入が日本の農業を圧迫したように見えますが、日本の農業が必要とする大豆粕肥料の需要が増加したことが背景にあり、日
本の農業技術の変化が、結果として国産大豆の生産を押し下げることとなったことに注目するべきでしょう。
(5)大豆搾油技術の変革-溶剤抽出法の登場
満州の大豆産業が活気を呈しているころ、新しい搾油技術として溶剤抽出技術がヨーロッパで開発されました。それまでの圧搾法では、100kgの大豆から約9kgの大豆油しか抽出できませんでしたが、この新技術により大豆に含まれる油分のほとんどを抽出できることとなりました。それは、大豆搾油の中心が中国(満州)から他の国に移動することを意味するものでもありました。
ヨーロッパで最初に溶剤抽出法を活用した大豆搾油を発展させたのはイギリスでしたが、やがてヨーロッパ大陸にも波及し、満州からの輸入大豆を搾油するようになり、ドイツが最大の大豆搾油国として名乗りを挙げ、日本(満州で操業する日本企業を含む)とともに世界の搾油業を牽引する存在となりました。
日本においても溶剤抽出技術の研究開発が進められました。南満州鉄道の研究所がこの問題に取り組み、満鉄豆油製造場で試験的製造を行い成功を収めました。しかし鉄道会社が搾油業を営むことは適切でないことから、1916年に満鉄豆油製造場と技術は鈴木商店(当時。その後の豊年製油)に譲渡され、同商店はその能力を拡大した大豆搾油工場を満州に建設しました(「育もう未来を ホーネン70年のあゆみ」(株)ホーネンコーポレーション)。
【 図6 鈴木商店の大連大豆搾油工場 】

【 図7 サイロではなく野積み状態の大豆 】
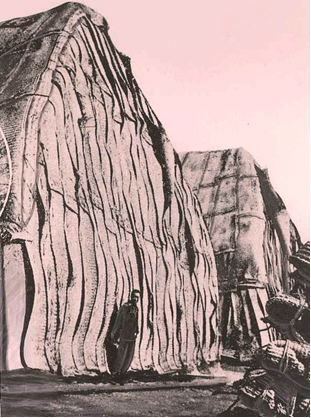
大連で先行して操業していた日清製油、三井物産、三菱商事などの各工場も新技術を取り入れた工場の建設を進めるとともに大豆油の精製工場建設をも進め、ここで漸く大豆油が食用に供される基盤ができ上がることとなりました。このとき開発された溶剤抽出技術は、溶剤としてベンゼンを用いるものでしたが、その後、南満州鉄道はアルコールによる抽出技術を確立し、同社の大豆搾油工場を建設しました。History of Soybean Crushingには、アルコール抽出した大豆油には仄かにアルコールの香りが残り、中国の人達がそれを好んだことを記しています。
満州の動きと併行して、日本国内においても溶剤抽出法を取り入れた近代的な搾油工場が、京浜、中部、阪神、北九州の各地に建設され、満州から供給される大豆や大豆油を原料とする大豆搾油、精製工場の建設が進展し、ここに現在の日本の製油産業の原型が形成されることとなりました。
日本の大豆搾油の黎明は満州がもたらしたものであり、「満州に咲いた大豆の花」と称してもよいのではないでしょうか。
|