一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
一般社団法人日本植物油協会は、
日本で植物油を製造・加工業を営む企業で構成している非営利の業界団体です。
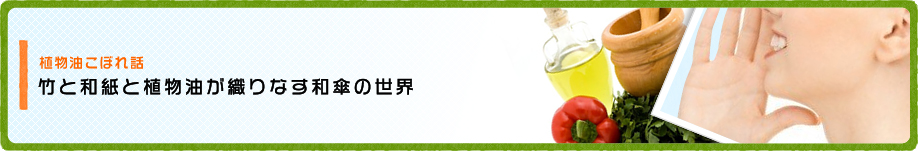
世界でも有数の降雨地帯の日本では、雨具は生活に欠かせないものでした。中でも代表的なものが和傘。生産地の岐阜市にうかがって、日本で独自の進化をとげた和傘と植物油との関わりをみてみましょう。
和傘は竹に張った和紙に、植物油を染みこませたもの。この油が水をはじくことで、雨具の役割を果たします。
蛇の目傘、番傘、日傘、舞い傘、踊り傘、野点(のだて)傘といった種類がありますが、防水の必要がない日傘などには油を塗りません。
傘は古代に中国より伝来しました。当時の傘は開閉ができず開きっぱなしのもの。その後日本で独自の発展をとげました。安土桃山時代に現在のような構造の和傘になりましたが、使用するのは特権階級に限られ、一般民衆に普及したのは江戸時代半ばからでした。
和傘は当初、京都や大坂で作られていましたが、やがて岐阜、江戸でも生産が始まり、全国各地へ広がっていきました。

和傘は唐傘ともいいますが、「中国から伝来したので唐傘」、「唐傘=からくり傘」など言葉の由来には諸説あります
和傘は、竹を割って軸と骨をつくり、それらを組み立てて、和紙を張ったあとに、植物油で防水加工をほどこしてできあがります。100を超える工程は、すべて職人の熟練の手技によるもの。防水のために植物油を用いるのは、仕上げ段階です。
岐阜和傘の老舗・マルト藤沢商店の藤沢健一さんは、「和紙に使われるコウゾは本来丈夫なものですが、油を塗ると、時間の経過とともに油の硬化作用で壊されてしまいます。厚く塗れば和紙の寿命は短くなり、薄く塗ると雨具の用をなしません」と、語ります。
荏油(えのあぶら)、亜麻仁油、桐油に、紙に油を浸透しやすくするために少量の鉱物油を混合して使用します。油と紙の相性を見極めながら、季節に応じて混合比率を変えなければなりません。
「戦前はいい傘には必ず荏油を使っていたものですが、あまりに高価なため最近では亜麻仁油を代用しているところがほとんどですね」(藤沢さん)
温めた油を布に染みこませ、塗るというより、なでるように引きます。このとき、厚く塗りすぎると折り畳んだ面がくっついて開けられなくなるので、細心の注意を払います。さらに和紙に油を十分に染みこませるために、一晩寝かせてから乾燥工程に入ります。

和傘は、100を超える工程を、十数人の職人の手仕事で作られます。岐阜和傘はこの分業制によって大量生産が可能になりました
岐阜は、製油発祥の地として知られる京都・大山崎で荏油の商人だった斉藤道三が、美濃(岐阜)城主になったところ。司馬遼太郎の「国盗り物語」で有名な戦国武将ですね。
もともと北部の飛騨地方は中世から荏胡麻(えごま)が栽培され、その種から絞る荏油は灯明用のほか、雨具の材料にも使われてきました。
岐阜で和傘づくりが盛んになったのは、江戸時代中期に加納藩(岐阜市南部)が財政難を克服するため、藩士に傘づくりを奨励したことによります。真竹、美濃紙、荏油など地元の産物を用いて、地場産業としての地歩を築いてきました。
1859年(安政6年)には年間生産本数は約50万本を数え、江戸、京都、大坂へも出荷され、全国にその名が知られるようになりました。明治以降は増産に拍車がかかり、1872年(明治5年)に150万本を記録。さらに1940年(昭和15年)の生産は約900万本に至りました。これは全国の生産数の25%にあたります。
増大する和傘の生産に対して、使用する植物油はどのように入手していたのでしょうか。昭和4年ころの資料によると、荏油は飛騨地方や北海道から供給を受けていたものの生産量が少なく、価格も高いため、北満州(中国東北地方)や朝鮮からも輸入していたとのこと。また、代用として亜麻仁油を用いるようになったことも記されています。

昭和50年代の油塗り風景。油を温めながら布に染みこませ、塗るというよりなでる感じで引きます。余分に塗りすぎると、乾きにくくなるほか、紙の劣化を早めます
第二次世界大戦で、岐阜市は焦土と化しましたが、和傘業界はいち早く立ち直り、昭和24、25年ころには年間1500万本以上と、戦前をしのぐ生産量を誇りました。岐阜県の荏胡麻の生産量が全国第2位(昭和24年)というように、地元の産物が後押ししたことが推察できます。
藤沢さんは、「洋傘を作ろうにも、鉄も布もありません。その点、和傘は地元の材料を利用できたので生産が伸び、復興に一役買うことができました。特異な状況だったんですね」と振り返ります。
ところが世の中が落ち着くにつれて、日本人の生活が洋風化し、昭和30年代に和傘と洋傘の生産数が逆転。やがて和傘は、日常生活の風景から消えていきます。
藤沢商店では現在、蛇の目傘や番傘など実用品としての和傘の製作は、全体の3割ほど。
「和傘は雨具としての役割をほぼ終えたと思います。高齢化によって、全国から和傘職人が消えていく中、各地の祭や芸能・行事に使用する和傘を何とかしてほしいという相談をよく受けるようになりました。そうした需要が高まっています」(藤沢さん)
250年の歴史をもつ和傘づくりの伝統をつぎの時代の残そうと、藤沢さんは、若手職人の養成などに力を注いでいます。

仕上げ職人が、天候の変化に注意を払いながら行う天日干し。「天気予報は、気象台より職人に聞け」といわれるくらい、よく当たります

お気に入りの蛇の目傘を手にする藤沢さん